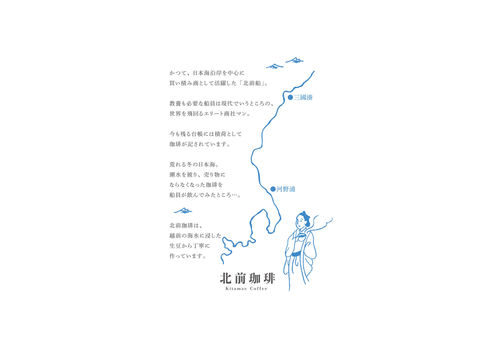+ヒトマメ
新幹線開業を2024年3月に控え、長野・岐阜からのアクセス向上のため中部縦貫自動車道も整備されつつある中、福井県内の各地域では観光施設の充実が図られている。県内随一の集客を誇る恐竜博物館へのアクセスとなる勝山ICからほど近い道の駅の敷地内に、「+ヒトマメ」と名前のつけられた店舗は地元の油揚げ製造会社(福井県は消費量全国一位)である山一食品の新規事業として整備。 報恩講を通じて大豆料理に親しみのある福井県。ここでは、県内外から訪れる人々に奥越の食文化のひとつである大豆食品の魅力を広め、人々の健康を担うために、油揚げだけではなく大豆を使った様々な料理やスイーツ、飲料が提供されています。 https://www.instagram.com/hitomame_2023/

八重巻酒店
ひと昔前は田園が広がっていた森田地区。福井市中心部から九頭竜川を越えた市境にあり、現在は人口増加が顕著な地域となっている。地区の中心には少しの商店や事業所、スーパーなどがあり、その一角にある森田駅は福井駅の隣駅で、県中心部での就業や買い物にとっては非常に利便性が高い。新幹線開通を2024年春に控えた福井ではJR在来線が地元に移管され、より地域交通の要となることが見込まれる。その森田駅の出口から真っすぐ50m行き、昭和23年福井地震における犠牲者慰霊の震災観音堂の隣地が本計画地となりました。 https://www.yaemaki.jp/ https://www.instagram.com/yaemaki/